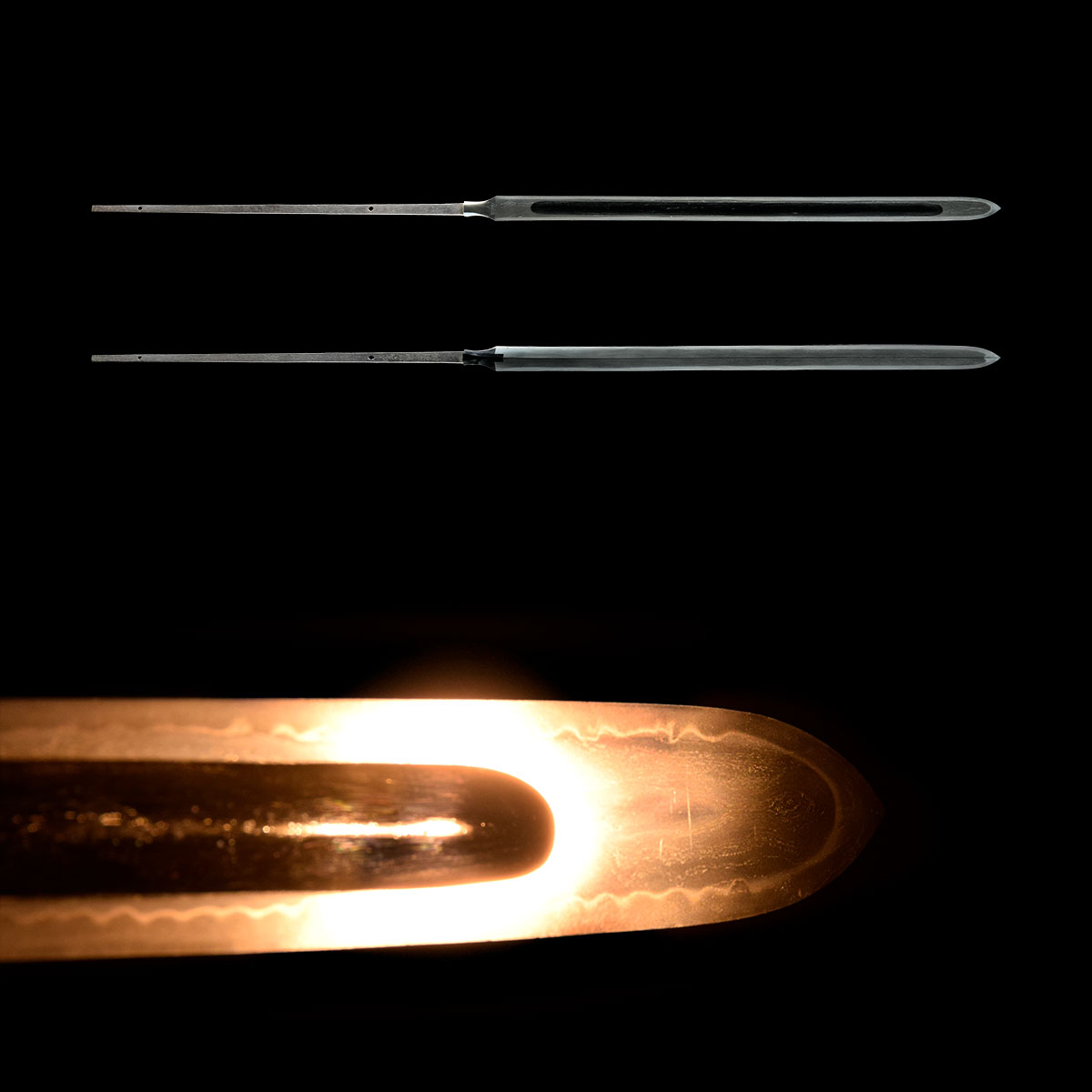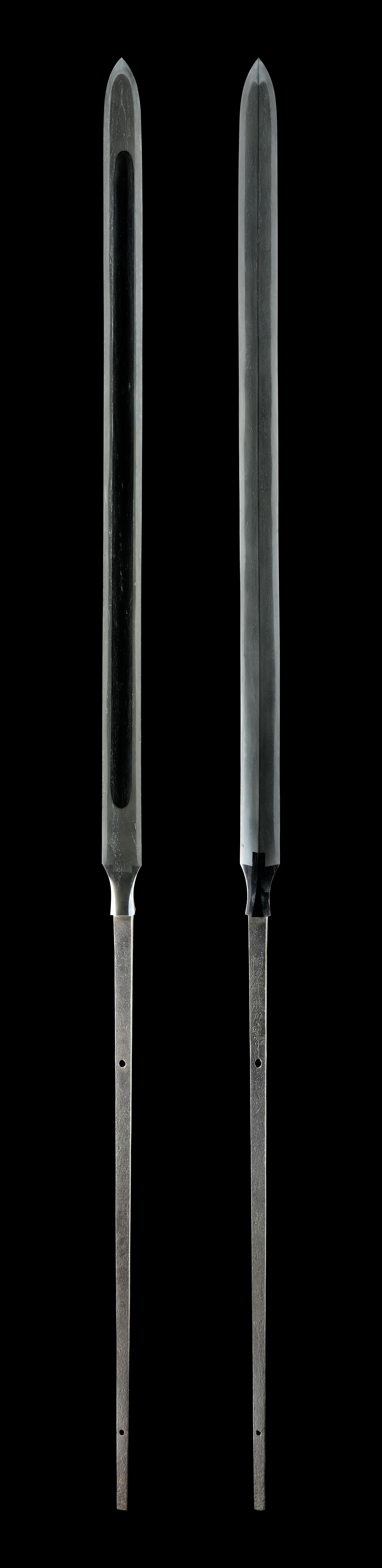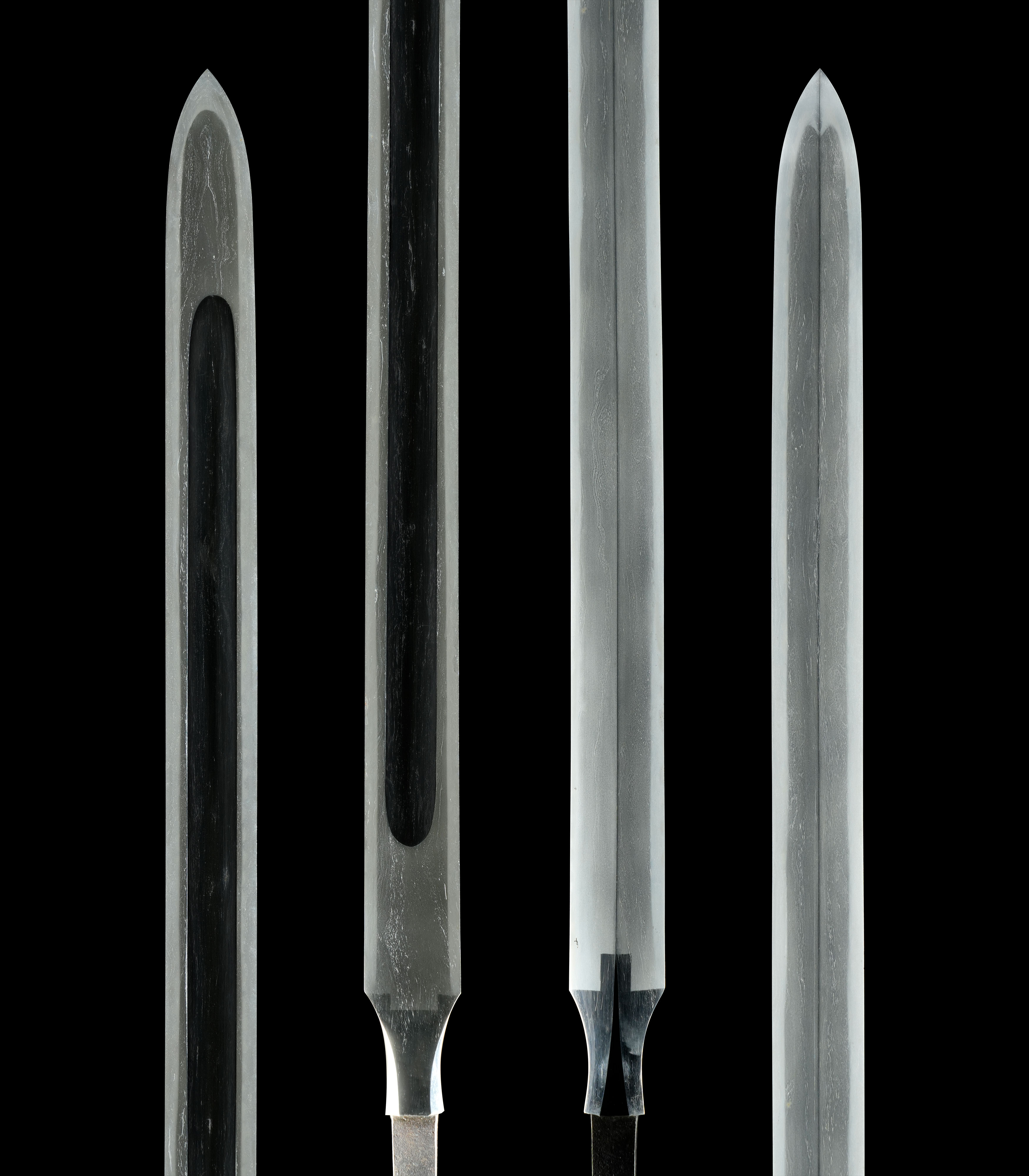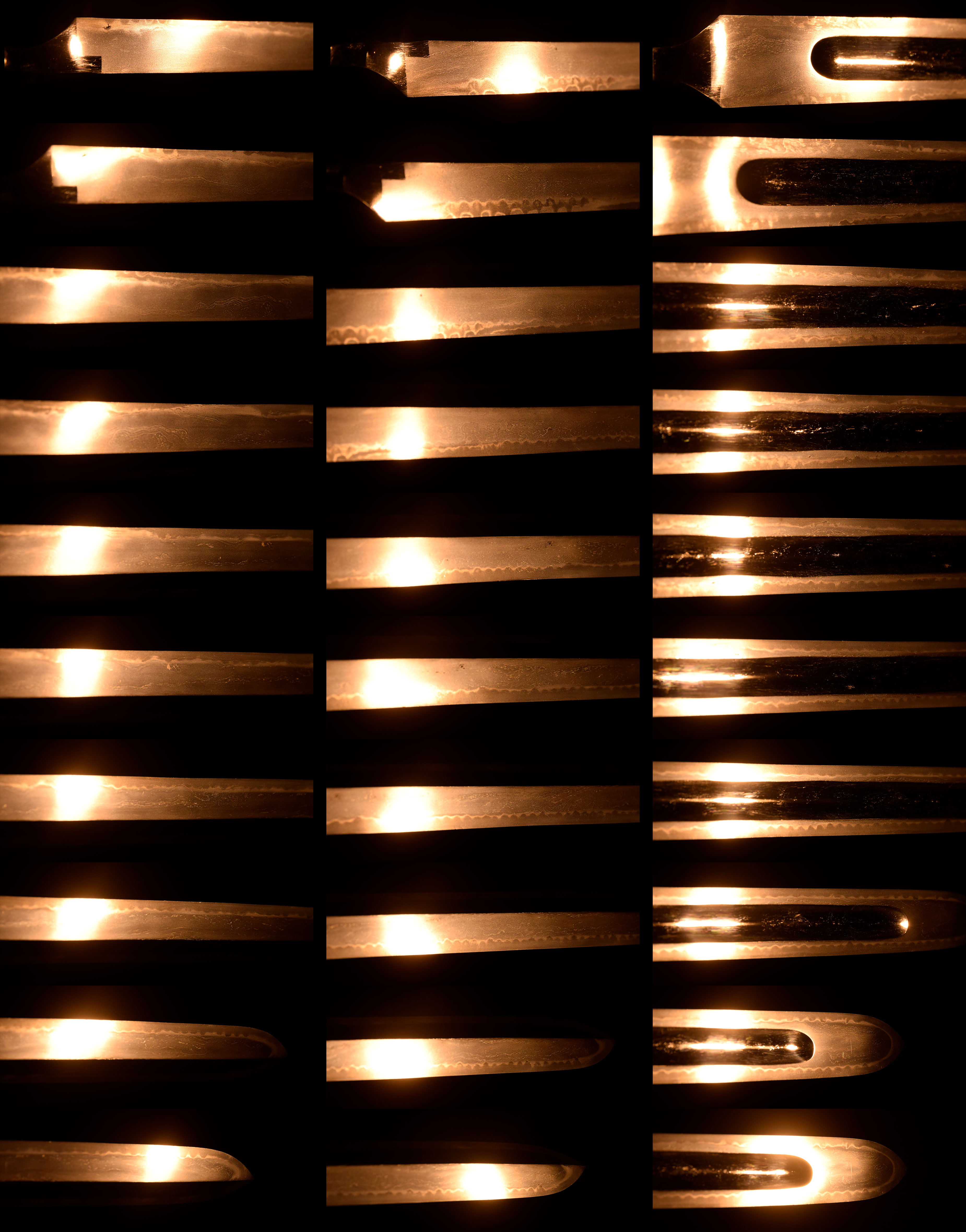相模守藤原政常 - Sagami no kami Fujiwara Masatsune - 6-069
¥660,000
税込
刃長77.4センチ
元幅34.6ミリ 元重ね11.2ミリ
物打幅33.8ミリ 物打重ね8.1ミリ
螻蛄首八角形 螻蛄首元幅21.5ミリ 螻蛄首元重ね21.4ミリ 螻蛄首の長さ43.3ミリ 茎の長さ51.0センチ
裸身重量1,198グラム
室町後期 The latter period of Muromachi era
平成6年11月24日 岐阜県登録
附属 白鞘
初代政常は、名を納戸佐助と称し、後に太郎助と改めた。美濃国鍛冶八代目奈良太郎兼常の末流、八代目納戸助右衛門兼常の次男として天分五年(1534)に美濃国納土(現在の関市千年町辺り)に生まれました。
永禄十年(1567)、三十三歳で春日郡小牧村に来住して独立、兼常と銘する。天正十二年(1584)の『小牧長久手の戦い』では、徳川家康の下で槍百筋を鍛えて家康より銀子を賜りました。
天正十九年(1591)関白豊臣秀次が清洲城主に就任すると、秀次の斡旋により、天正二十年(1592)五月十一日、信高が『伯耆守』、氏房は『飛騨守』、政常は『相模守』を受領。当時の尾張小牧領主であった池田輝政より『政』の字を与えられ兼常を政常に改銘したと伝う。
慶長五年(1600)十一月十七日、政常六十六歳の時に、徳川家康の四男である薩摩守松平忠吉が清洲城主になると同時に、福島正則の召に応じて小牧より清洲城下に移住し、慶長八年(1603)より忠吉の抱え鍛冶として仕えました。
慶長十二年(1607)三月、藩主松平忠吉の病没を悼んで一旦隠居するも、同年四月二十六日に家康の九男、徳川義直が清洲城主となり、政常は百石余の高禄を得て実子の二代と共に義直に仕えました。
同十四年(1609)実子である二代政常が早世したため、美濃国より大道の子(後の三代美濃守政常)を養子として迎え、自らは『相模守藤原政常入道』として復帰している。同十五年二月に名古屋城開府に伴い、名古屋城下富田町(現在の名古屋市中区桜通本町角)に移り、鍛刀に従事。元和五年(1619)二月二十八日没。享年八十五歳。
作刀年紀は天正二十年、慶長元年、二、三、六、九、十一年の裏銘があり、政常の作域中、刀は稀有で、槍・薙刀・小刀を盛んに鍛え、新刀中の雄、無双の名人として知られ、短刀は品位が高く、直刃の上出来は尾張新刀最上位と言われます。
本作は二尺五寸五分強の長大な大身槍で、平三角造。螻蛄首を八角形とし、螻蛄首がやや長い造り込みであることから、天正二十年以降の室町末期の間に鍛えられた一筋と考えられます。表面には太く長く双頭の樋を力強く掻き、地鉄は板目が柾に流れて杢交じり、地景入り、少しく肌立ち、刃文は互ノ目を焼き上げており、下の方では特に働きが盛んで、連なる互ノ目の中にもう一段連なる互ノ目が一際明るく現れ、そうした働きを伴う刃取り全体が、大きく食い違った感じの箇所があり、砂流かかり、刃中には足や葉が入って金筋現れ、小さな打除風の刃や湯走風の働きも見られる。鋩子は直ぐに先丸く返る。
室町末期から江戸初期に渡って活躍し、尾張新刀の礎を築いた初代相模守政常。数多の名工が槌を振るう中、特に槍・薙刀・短刀の名手としてその名を馳せた政常の手による大身槍は、まさに名槍中の名槍と位置づけられよう。
常に見る地鉄清涼たる小振りの平三角造りの作品とは異なり、戦国の時勢故に、やや大肌を伴った豪快な鍛えの地鉄であるところも、本槍の見どころの一つであり、見る者に強靭な生命力と迫力を伝え、幾多の戦をくぐり抜けた時代の息吹が宿った、まさに武の美学と時代の情熱が融合した一筋といえよう。
元幅34.6ミリ 元重ね11.2ミリ
物打幅33.8ミリ 物打重ね8.1ミリ
螻蛄首八角形 螻蛄首元幅21.5ミリ 螻蛄首元重ね21.4ミリ 螻蛄首の長さ43.3ミリ 茎の長さ51.0センチ
裸身重量1,198グラム
室町後期 The latter period of Muromachi era
平成6年11月24日 岐阜県登録
附属 白鞘
初代政常は、名を納戸佐助と称し、後に太郎助と改めた。美濃国鍛冶八代目奈良太郎兼常の末流、八代目納戸助右衛門兼常の次男として天分五年(1534)に美濃国納土(現在の関市千年町辺り)に生まれました。
永禄十年(1567)、三十三歳で春日郡小牧村に来住して独立、兼常と銘する。天正十二年(1584)の『小牧長久手の戦い』では、徳川家康の下で槍百筋を鍛えて家康より銀子を賜りました。
天正十九年(1591)関白豊臣秀次が清洲城主に就任すると、秀次の斡旋により、天正二十年(1592)五月十一日、信高が『伯耆守』、氏房は『飛騨守』、政常は『相模守』を受領。当時の尾張小牧領主であった池田輝政より『政』の字を与えられ兼常を政常に改銘したと伝う。
慶長五年(1600)十一月十七日、政常六十六歳の時に、徳川家康の四男である薩摩守松平忠吉が清洲城主になると同時に、福島正則の召に応じて小牧より清洲城下に移住し、慶長八年(1603)より忠吉の抱え鍛冶として仕えました。
慶長十二年(1607)三月、藩主松平忠吉の病没を悼んで一旦隠居するも、同年四月二十六日に家康の九男、徳川義直が清洲城主となり、政常は百石余の高禄を得て実子の二代と共に義直に仕えました。
同十四年(1609)実子である二代政常が早世したため、美濃国より大道の子(後の三代美濃守政常)を養子として迎え、自らは『相模守藤原政常入道』として復帰している。同十五年二月に名古屋城開府に伴い、名古屋城下富田町(現在の名古屋市中区桜通本町角)に移り、鍛刀に従事。元和五年(1619)二月二十八日没。享年八十五歳。
作刀年紀は天正二十年、慶長元年、二、三、六、九、十一年の裏銘があり、政常の作域中、刀は稀有で、槍・薙刀・小刀を盛んに鍛え、新刀中の雄、無双の名人として知られ、短刀は品位が高く、直刃の上出来は尾張新刀最上位と言われます。
本作は二尺五寸五分強の長大な大身槍で、平三角造。螻蛄首を八角形とし、螻蛄首がやや長い造り込みであることから、天正二十年以降の室町末期の間に鍛えられた一筋と考えられます。表面には太く長く双頭の樋を力強く掻き、地鉄は板目が柾に流れて杢交じり、地景入り、少しく肌立ち、刃文は互ノ目を焼き上げており、下の方では特に働きが盛んで、連なる互ノ目の中にもう一段連なる互ノ目が一際明るく現れ、そうした働きを伴う刃取り全体が、大きく食い違った感じの箇所があり、砂流かかり、刃中には足や葉が入って金筋現れ、小さな打除風の刃や湯走風の働きも見られる。鋩子は直ぐに先丸く返る。
室町末期から江戸初期に渡って活躍し、尾張新刀の礎を築いた初代相模守政常。数多の名工が槌を振るう中、特に槍・薙刀・短刀の名手としてその名を馳せた政常の手による大身槍は、まさに名槍中の名槍と位置づけられよう。
常に見る地鉄清涼たる小振りの平三角造りの作品とは異なり、戦国の時勢故に、やや大肌を伴った豪快な鍛えの地鉄であるところも、本槍の見どころの一つであり、見る者に強靭な生命力と迫力を伝え、幾多の戦をくぐり抜けた時代の息吹が宿った、まさに武の美学と時代の情熱が融合した一筋といえよう。
| 刃長(cm) | 77.4 (二尺五寸五分四厘二毛) |
| 反り(cm) | ― |
| 元幅 | 34.6ミリ |
| 元重 | 11.2ミリ |
| 先幅 | 物打幅33.8ミリ |
| 先重 | 物打重ね8.1ミリ |
| 寸法 | 螻蛄首八角形 螻蛄首元幅21.5ミリ 螻蛄首元重ね21.4ミリ 螻蛄首の長さ43.3ミリ 茎の長さ51.0センチ |
| 目釘孔数 | 2個 |
| 時代 | 室町後期 The latter period of Muromachi era |
| 鑑定書 | ― |
| 登録 | 平成6年11月24日 岐阜県登録 |
| 付属 | 白鞘 |
| 重量 | 裸身重量1,198グラム |